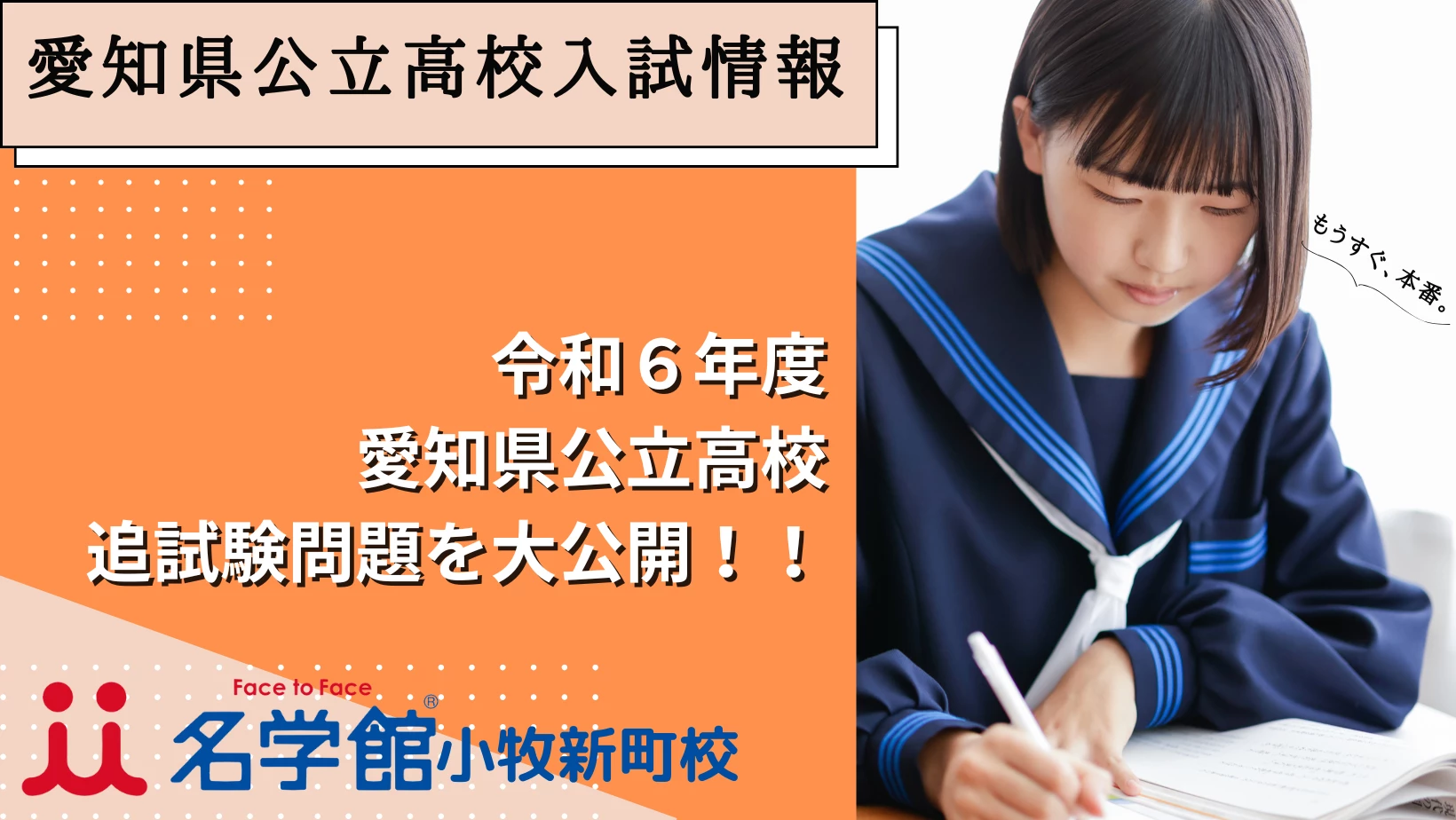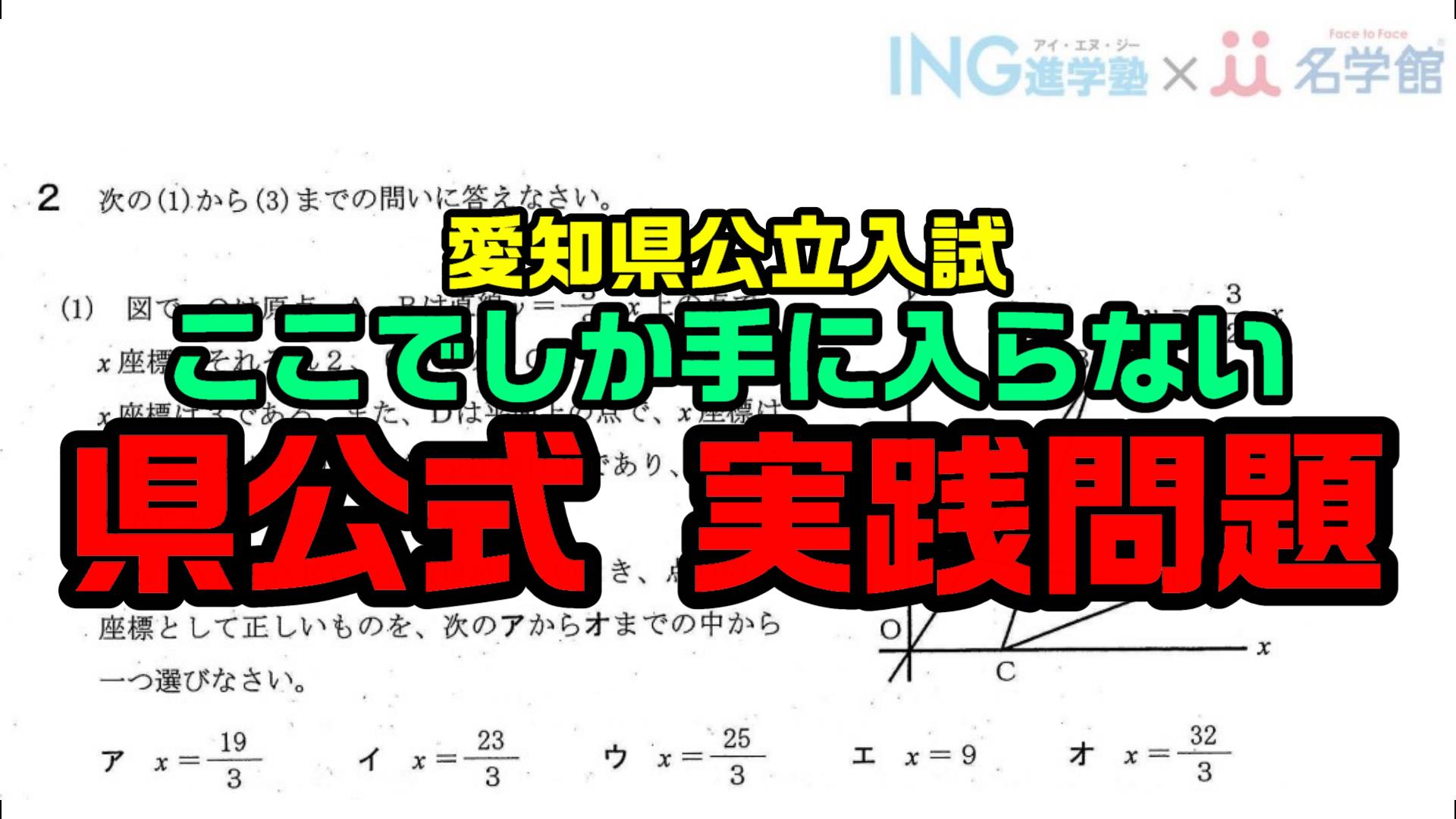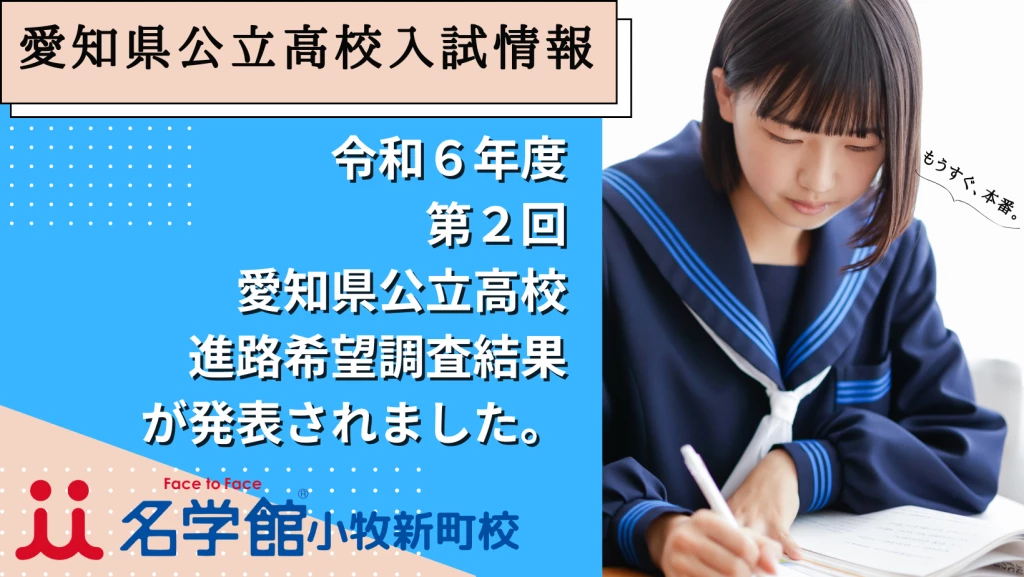2025年1月13日更新 リスニング音源追加
愛知県公立高校の入試情報をどこよりも詳しくお伝えする小牧市の個別指導学習塾
名学館 小牧新町校 塾長の吉澤です。
⇩⇩最新版令和7年度(2025年度)の追試験問題・解説はこちら⇩⇩

塾長
また、まだ独自ルートで追試験問題を入試しましたので、
英語、数学、理科
については大公開しちゃいます!!

飯田先生
先生!!
今年も、みんなに有益な情報バンバン出しましょう!!

塾長
ING進学塾飯田先生が今回、リスニング音声を作ってくれました!!
まずは、問題の公開からいきますね!!
解説も順次公開できればと思っています。
そして、國立先生と飯田先生の共著
『これだけ!!英単語360』の重版が決定しました!!


くにたて先生
これだけ英単語360の重版が決まりました!!

塾長
むちゃ早かったですね!!
おめでとうございます!!

飯田先生
まだ、実感がないですが、すごいことみたいですね💦
2024年度 令和6年度 愛知県公立高校 一般選抜 追試験 英語
全体傾向
- 問題構成は通常の一般選抜と類似しており、基礎力を重視した内容が多い。
- リスニング問題では、日常生活に関連する会話が中心となっており、自然な文脈での理解が求められる。ただ、今回第1問からいままでとは異なる地図から読み取る問題が出題された。
- 長文読解では、環境問題や社会的トピックなど、幅広い知識が役立つテーマが取り上げられた。
問題の傾向
- リーディング(読解問題)の重要性
- 長文読解問題では、社会問題や環境問題など実用的なテーマが扱われています。
- 図表や具体例を用いた内容理解が求められる問題が含まれています。
- リスニングに近い短文選択問題
- 会話の流れや日常のシチュエーションを想定した短文から、適切な選択肢を選ぶ問題が出題されています。
- 表やスケジュールを活用した応用問題
- 職場体験スケジュールやリストなどの実用的な資料を基に、正しい解釈が求められる問題が多いです。
- 日記形式の自由記述問題
- 設問の中には、日記の一部を完成させる問題があり、英語の文法や文脈理解力が試されます。
対策
リーディング力を鍛える
- 過去問演習を通して、長文の内容理解に慣れましょう。段落ごとに要点をまとめる習慣が効果的です。
- 環境問題や社会問題などのトピックを簡単にリサーチし、関連する英単語や表現を身につけると良いでしょう。
実用的な英語に触れる
- スケジュール表や図表を活用した問題は、細部まで読む力と全体像を掴む力が必要です。過去問を解く際は、表内の情報と設問を正確に結びつける練習をしましょう。
文法の基礎を押さえる
- 日記や会話文の補完問題では、文法の正確さがカギです。特に、時制や接続詞の使い方を意識してください。
多読とシャドーイングの実践
- 短文選択問題では、自然な会話の流れを理解することが重要です。日常英会話フレーズを多く学び、リスニング力も向上させましょう。
2024年度 令和6年度 愛知県公立高校 一般選抜 追試験 数学
問題の傾向
基本から応用まで幅広く出題
- 計算問題から関数、図形、立体図形まで、幅広い範囲をカバーしています。
- 特に、応用力が必要な問題(例えば複合的な条件を満たす解を求める問題や、図形の証明に近い問題)が含まれています。
記号選択型の解答形式
- マークシート方式のため、計算ミスがなくても選択肢に正しくマークする必要があります。
空間図形や立体図形の比率が高い
- 空間内の直線の関係、立体の体積や辺の長さなど、空間認識力が試される問題が出題されています。
図表やデータの読み取り問題
- グラフを基にエネルギー消費量を求めるなど、実用的なデータ活用問題が出されています。
対策
計算力の強化
- 四則演算や分数の計算をスピードアップさせる練習を繰り返し行う。
- ミスを減らすために計算過程を丁寧に書く習慣をつける。
空間図形の演習
- 立体図形や空間図形の面積・体積の公式を徹底的に理解する。
- 平面図形から空間図形への展開問題を解いて感覚を鍛える。
グラフやデータの読み取り練習
- グラフを素早く読み取り、必要な情報を抽出する練習を行う。
試験形式の模擬練習
- マークシート方式に慣れるために模擬試験を行う。
- 問題を素早く解く時間配分を意識する。
複合問題の練習
- 条件が複数ある問題に取り組み、条件を満たす解を見つける練習をする。
2024年度 令和6年度 愛知県公立高校 一般選抜 追試験 理科
問題の傾向
- 出題範囲の広さ
- 生物、化学、物理、地学の4分野からバランスよく出題されています。
- 基礎的な知識を問う問題と、応用力を試す問題が組み合わさっています。
- 図表の活用
- 図表やグラフを基にした考察問題が多く、データ読み取り力が問われます。
- 実験の結果や設定条件から答えを導く問題が見られます。
- 記述と選択の併用
- 選択問題だけでなく、計算や短い記述を求められる問題も出題されています。
- 計算問題では公式の適用だけでなく、単位換算や過程の理解も重要です。
- 日常生活や環境問題に関連する出題
- 環境問題、エネルギー利用、身近な科学現象を題材とした応用問題が含まれています。
主な出題分野とポイント解説
生物分野
「光合成に必要な条件を実験で示した結果を基に問われる問題」
- 解説: 光合成には光と二酸化炭素が必要であることをグラフや表から読み取る練習をする。
- 対策: 生物の基礎事項(光合成・呼吸・遺伝)を押さえつつ、図表問題に慣れる。
大問2では、「生態系における生物」に関する問題が出題されました。
重要な注意点
- この単元は、多くの中学校で2学期の期末テスト範囲となっておらず、まだ十分に対策できていない受験生が多い傾向があります。
- 食物連鎖や生態系のエネルギーの流れなど、理科に限らず3学期の学習内容も出題されるので手薄になっている分野はしっかり問題演習しておく。
2. 化学分野
「エタノールと水の混合物の問題」
問題の概要
- エタノールと水の混合液を加熱して沸騰する温度を測定し、それぞれの性質を考察する問題。
- エタノールと水の沸点の違いを利用した問題設定であり、蒸留や混合液の性質について理解を問う内容です。
解説
1. エタノールと水の性質を理解する
- エタノールの沸点:78.3°C
水(100°C)よりも低いため、加熱を続けるとエタノールが先に蒸発します。 - この性質を利用して、エタノールと水の混合液を蒸留し、それぞれを分離することが可能です。
2. 沸騰温度の変化
- エタノールと水が混ざっている場合、混合液の沸騰温度は両者の純物質の沸点の間になります。例えば、エタノールの割合が多ければ78.3°Cに近くなり、水の割合が多ければ100°Cに近づきます。
3. 蒸留の仕組み
- 問題では、混合液の加熱によって発生する蒸気を冷却することで、再び液体に戻す「蒸留」の考え方が問われます。このとき、蒸気中の成分比率が変化する点がポイントです。
3. 物理分野
「電熱線の電流と電圧の関係」と「磁界による力」
問題の概要
- 電流計と電圧計を用いた実験を通して、電流と電圧の関係や、電流が磁界から受ける力の大きさについて調べる問題。
- オームの法則や電磁力の基礎を理解する必要があります。
- 実験装置の構造や、得られたデータをグラフ化し、考察する力が求められます。
出題の意図
- オームの法則の理解
- 電圧、電流、抵抗の基本的な関係を正確に理解しているかを確認。
- 電磁力の基礎
- 電流が磁界中で受ける力の大きさや方向を、実験装置を通じて考察。
- データ分析と考察力
- 表やグラフを正確に読み取り、そこから意味を導き出す能力を問う。
4. 地学分野
「金星と月の見え方についての問題」
問題の概要
この問題では、以下の観点について考察する必要があります。
- 金星と月の相互位置関係
観測時点での金星と月の位置と、その見え方の変化を考察する。 - 月の欠け方
地球から見た月が欠けていく理由を基に、図や選択肢から正しい回答を導きます。
対策方法
- 天体の公転と位置関係の復習
- 地球と月、金星の位置関係を教科書や資料集で確認。
- 太陽系内の惑星がどのように動くのか、公転と見え方の関係を理解しましょう。
- 金星と月の満ち欠けを考える練習
- 月の満ち欠けに関する基本知識を復習。
- 金星も同様に満ち欠けが起こることを理解し、図やデータをもとに説明できるようにする。
- 図を用いた問題演習
- 天体図や位置関係を示す図を使い、金星や月の動きに基づいて正しい結論を導く練習を行いましょう。