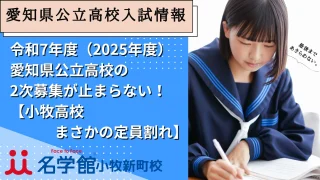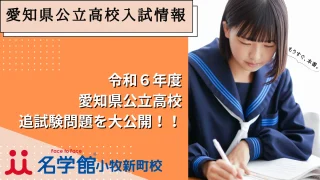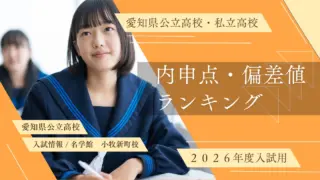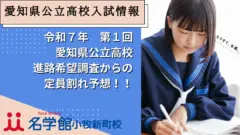愛知県公立高校の入試情報をどこよりも早く、詳しく発信する小牧市の個別指導学習塾
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

今年の追試験問題は本試の速報と同様に5教科全部公開します!!
しかも、社会の写真は独自にイラストを作成して公開!!
さらに、リスニング音源も入手しております!!

昨年はリスニング音源作るの大変でした💦
愛知県公立高校の追試験(追加選抜)は、一般選抜で惜しくもあと一歩届かなかった生徒にとって、最後のチャンスとなる重要な試験です。
しかし、追試験の問題や正答は公表されないため、実際の出題傾向を知る機会はほとんどありません。
名学館小牧新町校では、毎年独自に追試験の内容を分析・整理し、翌年度以降の受験生にも役立つ情報を発信しています。
昨年度(令和6年度)は英語・数学・理科の3教科のみの公開でしたが、今年(令和7年度)は国語・社会を加えた全教科を掲載しました。
著作権の関係上、国語の問題文は一部モザイク処理を行い、
社会の写真資料はChatGPTで作成した独自イラストに差し替えるなど、
実際の出題形式に近い形で問題を確認・解答できるよう工夫しています。
今回の追試分析は、追試を受ける生徒だけでなく、2026年度に一般選抜を受験する中学3年生にとっても非常に参考になる内容です。
出題傾向を早い段階で把握し、苦手分野を見直すことで、来年度の合格可能性を高めることができます。
ぜひ、今年度の追試問題・正答・分析を、今後の学習計画にご活用ください。
⇩令和7年度の2次募集情報はこちら⇩
⇩令和7年度本試験の解答速報はこちら⇩
⇩令和6年度追試験問題・解説はこちら⇩
⇩2025年 2026年度入試用 愛知県公立高校 私立高校 偏差値・内申点 ランキング一覧はこちら⇩
国語
【大問一】評論文
テーマ:自分を「デザインする」ことと他者との関係
SNSやVRなど、現代のコミュニケーション環境を背景に、「自己デザイン」=自分をどのように表現するかというテーマが論じられました。
筆者は、自己を自由にデザインできる現代社会の利点を認めつつも、“他者の視点や承認があってこそ自分の存在が確立する”という考えを提示しています。
自己表現の自由と、他者との関係性のバランスが主題でした。
- 内容理解問題(段落の要旨や筆者の主張の把握)
- 語句の意味や文中表現の解釈
- 選択肢問題では「筆者の意図」を正確に読み取る力が必要
一般選抜に近い難易度で、文章量もやや多めでした。
- 日頃からニュースや評論文に触れ、“他者の立場から物事を考える”練習を。
- 抽象的な表現が多いため、具体例や比喩を手がかりに要点をつかむ練習をしておくと良い。
- 模試の現代文でも、筆者の主張と自分の考えを分けて読む習慣を身につけましょう。
【大問二】漢字・語句
テーマ:基礎力を問う知識問題
例年通り、文章中の語彙理解や適切な漢字選択が中心の構成。
「語彙力」「熟語の意味」「正しい字形」など、日常的な学習の定着度が問われました。
読み・書き・意味の3パターンをバランスよく出題。
難読漢字は少なく、教科書・ワークレベルの知識で十分対応可能。
- 普段の授業や課題で出た語句を「自分で使えるレベル」に。
- 書ける・読めるだけでなく、「意味」まで説明できるようにするのが理想。
- 漢検準2級程度の範囲をカバーしておくと安心です。
【大問三】説明文・評論文
テーマ:「オリジナル」と「コピー」から考える創造の意味
美術や文化における「オリジナル」と「コピー」の関係を通じて、「創造とは何か」「模倣に価値はあるのか」を問う文章でした。
筆者は、“模倣(コピー)も新しい創造の出発点になりうる”と主張しており、表面的な違いではなく、「本質的な価値の見極め」がテーマになっていました。
- 比較・対比構造の把握
- 段落構成と論理展開の理解
- 「筆者の考えを最もよく表す一文」を選ぶタイプの設問も出題
- 現代社会や文化的テーマに関する文章に慣れておくことが重要。
- 「対比」や「抽象と具体」の関係を意識して読む練習を。
- 論理展開を意識して段落ごとに要約する習慣をつけましょう。
【大問四】古文
出典:『論語』の一節(孔子と弟子の対話)
孔子とその弟子・公冶長(こうやちょう)のやり取りを通して、人としての「笑い方」や「節度あるふるまい」が描かれています。
“真の教養とは、他人を馬鹿にする笑いではなく、思いやりをもって人と接する姿勢である”
という教訓的な内容でした。
- 語彙の意味(「然る後」「伝ふ」など)
- 登場人物の心情理解
- ことわざ的表現の意味を問う設問
- 『論語』『徒然草』『枕草子』などの代表的古典を一度読んでおくと安心。
- 古文単語の基本100語程度を定着させることで、設問理解が大幅に楽になります。
- 主語・述語を意識して文構造をとらえる練習を重ねましょう。
数学
【大問1】小問集合(計算問題)
四則計算、平方根、因数分解、方程式、比例・反比例など、中学3年間の基本計算力を幅広く問う問題でした。
式変形や符号の処理、分数の計算など、ミスを防ぐ正確さとスピードが求められました。
- 例年どおり、1問1点前後の短答式。
- 分数・平方根・文字式の混在が多く、途中計算を丁寧に行うことが重要。
- 教科書レベルの標準問題中心で、全体として「やや易」。
- 「一問一答形式」の計算練習を繰り返すことが効果的。
- ケアレスミス防止のため、符号や分母分子の整理を習慣化。
- 模試や過去問で制限時間内に8〜9割正答できるよう練習を。
【大問2】関数(一次関数・二次関数)
(1) は、マス目上の数字を塗りつぶす確率を求める問題。
(2) は、2つの放物線の面積条件から a の値を求める問題。
(3) は、駅とテーマパークを結ぶバスの動きをグラフで表し、距離や追い越し回数を考える問題でした。
いずれも、条件を整理して関係を式や図で表す力が求められました。
- 複数の条件を整理して筋道立てて考える力を問う良問構成。
- (1) は場合の数、(2) は関数の対称性、(3) は速さのグラフと、思考の幅が広い。
- 計算力だけでなく、論理的な整理力と図解力が得点のカギ。
- 確率や速さの問題は、まず図や表で状況を可視化。
- 関数は、条件を式で正確に表す練習を積む。
- 複雑に見える問題も、段階的に整理すれば解ける構成なので、焦らず丁寧に手順を追うことが重要です。

必ず自分で図・グラフを描く練習をしましょう!!
【大問3】平面図形・空間図形
(1) は、台形の相似関係と角度の性質を利用して、角の大きさを求める問題。
(2) は、直角三角形に半円を組み合わせた図形の長さと面積の関係を扱う問題。
(3) は、立方体をもとにした立体図形の体積を求める内容で、回転体の考え方を含む応用的な出題でした。
いずれも、図形の構造を正確にとらえ、相似・面積比・体積の関係を整理する力が求められました。
- 作図や補助線を使って関係を明確にできるかが鍵。
- 平面図形から立体へと発展する構成で、思考のつながりを意識させる出題。
- 計算よりも、図形の見方・考え方を問う良問。
- 相似・円・三平方の定理など、基本の結びつきを意識して学習する。
- 複雑な立体は「平面で分けて考える」習慣を。
- 回転体や空間図形の問題では、図を丁寧に描き直すことが正答率向上の鍵です。
社会

2025年度の追試験「社会」は、全6大問で構成され、歴史・地理・公民・現代社会の課題をバランスよく出題。
単なる暗記ではなく、資料やデータを読み取り、理由づけて考える力を重視する問題が目立ちました。
【大問1】金属を用いた日本の道具と文化の発展
金属器を題材に、日本の歴史の流れと文化の発展を問う問題。
銅鐸・和同開珎・茶釜などの資料をもとに、それぞれの時代背景と用途を正しく読み取る力が試されました。
- 資料(写真)をもとに時代を特定するタイプの定番問題。
- 弥生時代・奈良時代・室町時代など、金属文化と時代のつながりを問う構成。
- 語句暗記ではなく、用途・時代・文化の関連性を理解しているかが鍵。
- 教科書の「資料写真」に注目して、道具と時代をセットで覚える。
- 特に、弥生の銅鐸・奈良の貨幣・室町の茶の湯文化など、金属器と文化の組み合わせを整理しておく。
- 資料問題は毎年出やすいため、写真で見分けられる練習が得点アップのポイント。
【大問2】近代日本と国際関係の変化
イギリス・清・インドの貿易関係をもとに、アヘン戦争や鎖国の終焉、日本の開国後の経済変化を考える問題でした。
貿易構造や物価の推移、条約改正、戦後国際関係など、経済と外交の両面から近代史を整理する力が求められました。
- 資料グラフや貿易図を読み取り、原因と結果をつなげて考える構成。
- 「開国 → 貿易開始 → 物価上昇 → 条約改正 → 国際的地位の回復」という時代の流れを理解しているかがポイント。
- 経済史と外交史を融合した出題で、思考力を重視。
- グラフ問題は「何が増え・減ったか」「原因は何か」をセットで考える。
- アヘン戦争、日米修好通商条約、条約改正などの出来事の順序と意義を整理しておく。
- 現代の国際関係(冷戦・国際連合など)につながる流れとして学ぶと理解が深まります。
【大問3】関東地方の地形と産業の特色
グラフや地形図を用いて、関東地方の産業構造・地形・人口分布を読み取る問題。
製造業・農業・小売業の比較や、等高線・断面図の分析を通して、地理的条件と人々の生活の関係を理解する力が求められました。
- 複数の資料(グラフ・地図・断面図)を関連づけて考える力を問う。
- 工業地帯・平野・火山地形など、関東地方の地理的特徴をもとにした出題。
- 人口や社会増減率の資料も含まれ、地理と社会の融合的内容。
- 資料問題では、「どの地域を表しているか」を産業構成や地形から推定する練習を。
- 関東地方は地形・人口・産業のバランスが問われやすく、地図帳を活用した復習が効果的。
- グラフや等高線の読み取りに慣れておくと、全国地理にも応用できます。
【大問4】アフリカ州の気候・産業・貿易
アフリカ州の地図や気候グラフ、人口・貿易資料を用いて、気候帯・資源・人口変化の特徴を読み取る問題でした。
地域ごとの気候の違いと、輸出品目(原油・ダイヤモンド・カカオ豆など)を結びつけて理解する力が求められました。
- 複数資料(地図・気温・降水量・統計表)を組み合わせて考察する問題構成。
- 気候帯の南北分布、主要河川(ナイル川など)の流域と気候の関係を問う。
- 経済問題では、一次産品中心の輸出構造を通してアフリカの課題を考察させる内容。
- 気候グラフの読み取り(乾季・雨季・気温変化)を正確にできるように。
- 各国の主要輸出品を「地域+産品」で覚えると効果的(例:ナイジェリア=原油、ボツワナ=ダイヤモンド)。
- アフリカ州は「人口増加・資源・開発格差」など、現代社会にもつながるテーマとして整理しておくと理解が深まります。
【大問5】市場経済と公共サービスの仕組み
ガソリンや水道料金、レタスの価格変動などをもとに、市場価格と公共料金の違いを理解する問題でした。
また、デジタル行政サービスや保育所の統計資料を通じて、行政の役割と社会の仕組みを考えさせる内容になっています。
- 「市場経済」「独占禁止法」「公共料金」「情報リテラシー」など、
- 公民分野の基本用語を実生活と結びつけて問う構成。
- 複数の資料を比較して、価格変動・行政サービス・統計の意味を読み取る力が必要。
- 近年の入試傾向に沿った「データ活用型・思考力重視」の問題です。
- 公共料金と市場価格の違いを、**「誰が決めるか」「変動のしやすさ」**で整理。
- 経済用語(自由競争・独占禁止法など)は、日常ニュースと関連づけて理解する。
- デジタル行政や保育所のデータ問題は、統計を根拠に判断する練習が得点の鍵。
【大問6】選挙制度と国会の仕組み
選挙制度の違い(小選挙区制と比例代表制)や、国会の仕組み(二院制・議員の役割)について理解を問う問題。
実際の投票結果をもとに、得票数と議席数の関係や、衆議院と参議院の役割の違いを考えさせる構成でした。
- 小選挙区制と比例代表制の違いを、具体的な数値で比較する実践的な出題。
- 衆議院・参議院の権限や仕組みを、条文や議会制度に即して問う。
- 「国会議員の二院制」「両院協議会」「国会議員の特権」など、政治の基礎知識の定着度が試されました。
- 小選挙区制は「地域代表型」、比例代表制は「政党支持型」と整理して覚える。
- 衆議院は「任期が短く、国民の意見を反映しやすい」、参議院は「長期的・安定的な判断」と対比で理解。
- 政治の単元は暗記ではなく、制度の目的や仕組みを具体例で説明できるかがポイントです。
理科
【大問1】人体のしくみと化学反応の法則
前半は「血液の循環と尿の生成」に関する問題で、血管を通る血液の性質や尿素の濃度を比較する内容でした。
後半は「亜鉛とマグネシウムの反応実験」で、発生した気体の体積から混合比を求める計算問題が出題されました。
- 生物分野と化学分野の融合問題。人体の循環図は定番ながら、尿素の濃度比較で理解度を問う構成。
- 化学では、気体の体積比から物質の割合を求める実験考察型で、データ処理力を試す出題。
- 計算だけでなく、「表やグラフをどう読み取るか」という考察力がカギ。
- 生物分野では、血液の流れの順番と臓器の働きを図で説明できるように。
- 化学分野では、気体の発生実験を「比例関係」として整理する練習を。
- 思考力問題が中心のため、理由を自分の言葉で説明する練習を取り入れましょう。
【大問2】植物の分類と光合成のはたらき
イヌワラビ・ゼニゴケ・タンポポ・スズメノカタビラ・マツの5種類を比較し、**植物の分類と特徴(種子・維管束・双子葉類など)**を考察する問題でした。
後半では、タンポポを使った実験を通して、光合成と呼吸の関係を確認する内容でした。
- 植物の分類(コケ・シダ・種子植物)を特徴ごとに整理できているかを問う基本問題。
- 実験問題では、光の有無による二酸化炭素濃度の変化を根拠に、光合成と呼吸の違いを考える構成。
- 「グラフ+実験+分類表」の3要素が組み合わされた、思考型の良問。
- 分類問題は、**「胞子でふえる植物」「種子でふえる植物」**を整理して覚える。
- 光合成の実験では、「光がある→二酸化炭素減少」「光がない→二酸化炭素増加」の関係を押さえる。
- 植物の仕組みは図で覚えると効果的。葉のつくり・根の吸収・気孔の働きも関連づけて復習を。
【大問3】物質の溶け方と温度の関係
硝酸カリウムの溶け方を調べる2つの実験(温度変化と再結晶)に関する問題でした。
実験1では、温度によって溶解量が変化する様子を観察し、
実験2では、溶かした溶液を冷やすことで再び結晶が出てくる理由を考察させる内容です。
- 溶解度と温度の関係を扱う中学理科の定番テーマ。
- 図・表・グラフ・操作手順の全てを正確に読み取るデータ処理型問題。
- 計算問題も含まれ、実験の流れ(溶かす→加熱→冷却→ろ過)を理解しているかが問われました。
- 溶解度は「温度が上がるほど多く溶ける」が基本。グラフの傾きも確認する練習を。
- 冷やして結晶が出る=再結晶の原理を理解しておくと、応用問題にも強い。
- 実験図やグラフ問題では、「どの操作がどの目的か」を自分の言葉で説明できるように。
- 溶け方の単元は、実験操作+計算+現象の理解をセットで押さえるのが得点アップのコツ。
【大問4】滑車のはたらきと仕事の関係
この問題では、定滑車・動滑車・つる巻きばねを使った実験を通して、
「力の大きさ」「動く距離」「仕事(力×距離)」の関係を調べる内容でした。
それぞれの実験でモーターの出す力や時間を比較し、仕事や仕事率を計算します。
- 力学分野の基本である「滑車の原理」と「仕事の関係式(仕事=力×距離)」を問う定番問題。
- 図をもとに力の伝わり方や動く距離の違いを整理できるかがポイント。
- 実験4では、つる巻きばねを使って弾性力と仕事の関係を求める発展的計算問題が出題。
- 定滑車=力は変わらず向きだけ変える
動滑車=力は半分になるが距離は2倍
という関係を確実に理解しておくこと。 - 仕事の計算は単位に注意。「N×m=J(ジュール)」を常に意識。
- 問題文に「一定の速さ」「摩擦を無視」とある場合は、力のつり合いが成り立つと考える。
- 図中の動き方をイメージしながら、「力が小さくなれば距離が大きくなる」関係を確認しよう。
【大問5】天気図と前線の通過にともなう天気の変化
この問題では、天気図の読み取りと気象データの分析を通して、前線の通過にともなう「気温・風向・降水・湿度」の変化を考察する内容でした。
名古屋を観測地点として、3日間の気象データ(気温・風向・降水量など)から前線A・Bの通過時刻や天気の変化を推定する総合問題です。
- 温暖前線」「寒冷前線」の特徴(気温変化・雨の降り方・風向の変化)をデータと照らし合わせて判断する問題。
- 表データの読み取りに加え、湿度・気圧・飽和水蒸気量の関係も問われ、計算と記述の両面から理解を確認する構成。
- 図表・数値・風力記号・天気図を組み合わせた実戦的な複合問題でした。
- 温暖前線:通過前に雨が長く続き、通過後に気温が上がる。
- 寒冷前線:通過時に強い雨、通過後に気温が下がる。
- → この「気温・雨の降り方・風向」の3点セットで判断するのがコツ。
- 湿度の問題では、実際の水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量 × 100 の式を必ず覚えておく。
- データ読み取り問題では、グラフや表に線を引きながら
- 「どこで急変しているか」を目で追う練習が有効。
【大問6】電流がつくる磁界と金環食のしくみ
🧲(1)電流のつくる磁界
コイルに電流を流したとき、まわりの方位磁針の向きがどう変化するかを観察する問題です。
電流がつくる磁界の向きと、針の向きの変化を通して右ねじの法則を確認します。
- 毎年のように出題される磁界の向きの基本問題。
- 方位磁針がどの方向を指すかを、上から見た図でイメージできるかがポイント。
- 「コイルに電流を流す→磁界発生→針の向きがずれる」という因果関係を理解しておくことが重要です。
- 右ねじの法則:電流の向きに親指、磁界の向きに指を巻く。
- → コイルの中はN極、外はS極になる向きに針が回転します。
- 問題のように方位磁針を複数配置したときは、磁界の「円の広がり方」を意識して考えるとわかりやすいです。
- 実験図の上から見た視点を混乱しやすいため、ノートで俯瞰図を自分で描く練習をしておくと◎。
(2)金環食のしくみ
地球・月・太陽の位置関係をもとに、金環食が起こる条件を式で表す問題です。
太陽と月の見かけの大きさの比較をもとに、距離と直径の比を用いた関係式を選びます。
- 地学分野で近年よく出る「見かけの大きさ」「比例関係」を問うパターン。
- 文章を読んで関係式(D, R, d, r の比)を立てられるかがカギ。
- 金環食と皆既日食の違いを理解していないと間違えやすい設問です。
- 太陽が月よりも「わずかに大きく見える」と金環食になる。
- → 見かけの大きさは「直径 ÷ 距離」で決まる。
- → よって、D/R > d/r が金環食の条件。
- 反対に「皆既日食」は D/R < d/r となる。
- 図を見て、地球→月→太陽の順での距離関係を正確にとらえる練習をしておこう。
英語
英語 聞き取り音源

昨年度の追試験の音源は
ING進学塾の飯田先生に作成頂きましたが今回は音源の入手ができました。
ダウンロードもできるので、是非ご活用ください。

リスニングの勉強法については後ほどブログで紹介させてもらいます!!
英語筆記試験解説
【大問1】会話文
健太(Kenta)とアメリカからの留学生トム(Tom)の会話文。
留学生の日本での学校生活や驚いたこと、別れのシーンを通して、
自然な英会話の流れや文脈理解を問う問題です。
3つの空所補充((1)〜(3))はすべて文脈の一貫性と会話表現の自然さがカギでした。
- 会話の流れに沿って、文脈から適切な英文を選ぶ問題。
- 感情表現(I’m happy / I’ll miss you / Thank you so much)など、
- 人間関係や日常英会話でよく使われる表現が中心。
- 文法力よりも、内容理解・会話のつながりの把握が重視されました。
- (1) は “Especially, ____.” の文脈から、
食事を話題にしているため 「一緒に昼食を食べたのが楽しかった」= eating lunch together was a lot of fun が自然。 - (2) は “At first, it was a difficult challenge because I ____.” から、
「満員電車が苦手だった」= couldn’t stand the crowded train が最も適切。 - (3) は “Staying in Japan was a good ____ for me.” の流れから、
「よい経験だった」= a good experience が自然な選択。 - → つまり、答えは (1) イ (2) エ (3) ア が最も文脈的に自然です。
- 空所補充問題では、直前直後の文脈を丁寧に読むことが最重要。
- 特に “especially” “at first” “a good ~ for me” など、文型・副詞表現がヒントになっている場合が多い。
- 「日本での留学体験」というテーマから、感情表現・文化比較・あいさつ表現の定型を覚えておくと得点源になります。
【大問2】長文読解(南極に関する説明文)
南極(Antarctica)をテーマにした説明文読解。
人が住めない理由、環境の厳しさ、科学者による研究、
そして「南極条約」による国際的な取り決めについて述べられています。
文章量が多く、内容理解+設問の選択肢処理の両方が求められる思考型長文です。
(1) 文脈補充(but ①)
(2) 並べかえ問題(②)
(3) 接続語補充(A)
(4) 条約内容の把握
(5) 内容一致(2つ選択)
- 長文全体が「環境・国際協力・科学研究」という近年の定番テーマ。
- 単語レベルは標準ですが、構文が長く、主語・動詞の対応を追う力が求められました。
- 設問(5)のような内容一致問題は、本文をざっと読むだけでは落としやすく、
- 「根拠となる英文を見つけて確認する」練習が重要です。
- 専門的な単語(permanent, Treaty, melt など)も、文脈で意味を推測できるようにしておきましょ
【大問4】会話文+表まとめ+日記文記述(ロボットの良い点・悪い点)
日本の中学生・亮(Ryo)と、ドイツからの留学生・エマ(Emma)の会話。
授業で「ロボットの良い点と悪い点」について発表する内容を話し合う形式です。
後半は会話の内容を表に整理する問題や、
亮がその日の出来事を日記でまとめた英文完成問題もあり、
読解力+要約力+文法力がすべて問われる構成になっています。
1.ロボットの良い点
→ 休まずに長時間働ける・危険な作業を代わりにしてくれる
2.ロボットの悪い点
→ 高価で点検が必要・人の仕事が奪われる可能性
3.将来の展望
→ 人々はロボットの使い方を変えていくだろう、という前向きな結び
- 会話・表・日記という三段構成型問題。
→ 単なる英文読解だけでなく、内容を整理してまとめる力が求められました。 - 特に (3) の表問題は、どの情報がどの立場(Workers / Companies)に属するかを区別できるかが鍵。
- (4) は文章構成力+文脈理解力を問う「応用型英作文」。
英語聞き取り検査解説
2025年度の英語リスニングは、**第1問(会話文)と第2問(スピーチ)**の二部構成でした。
音声スピードは約110〜125 wpmで、昨年度と同程度。
発音は明瞭で、語彙も教科書レベル中心のため、聞き取りやすい構成でした。
第1問:
男女の会話形式で、学校生活や学習テーマに関する短いやり取り。
→ 現在完了・過去形・進行形など、基本的な文法を自然な会話で確認する内容。
第2問:
生徒Masatoによるスピーチ形式。
テーマは「部活動での経験」や「仲間とのコミュニケーション」。
→ learn from losing, decided to communicate more など、英検準2級レベルの表現も登場。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 発音の明瞭さ | ★★★★★(標準アメリカ英語で聞き取りやすい) |
| 音声速度 | ★★★☆☆(中学教科書レベル) |
| 思考力要求度 | ★★★★☆(内容理解型が中心) |
| 難易度 | 英検3級〜準2級(CEFR A2〜B1) |
👉 今年は「単語を聞き取る力」よりも、内容を理解する力を問う傾向が強くなりました。
- スクリプトを読む+音声を聞くを組み合わせると効果的です。
→ 聞き取れなかった箇所をスクリプトで確認し、音のつながりを意識する。 - 英検3級・準2級のリスニングPart2, 3で練習すると本番形式に近い。
- “decided to〜” や “learn from〜” のような構文は、スピーチ定番表現として覚えておくとよい。
今年のリスニングは「速さ」よりも内容理解に重点がありました。
これから入試を目指す生徒は、ただ聞くのではなく「どんな場面で、何を伝えようとしているのか」を考えながら練習することが重要です。
英語の聞き取りは短期間では身につきにくいため、
毎日の学習の中に少しずつ音声教材を取り入れるのがおすすめです。
教科書についているQRコードから音声が聞けるので、活用しましょう。
リスニング台本全文
第1問
第1問 1番
Michael: Yes, Ms. Baker. Is Mr. Jones here in the teachers’ room now? I have some questions about today’s class.
Ms. Baker: Oh, he’s in a meeting with the other science teachers.
a. He is teaching science with Ms. Baker.
b. He is talking with Ms. Baker.
c. He is walking to his classroom.
d. He is asking Mr. Jones some questions.
和訳:
ベイカー先生:「こんにちは、マイケル。どうしたの?」
マイケル:「こんにちは、ベイカー先生。ジョーンズ先生は職員室にいますか? 今日の授業についていくつか質問があります。」
ベイカー先生:「あら、ジョーンズ先生は他の理科の先生たちと打ち合わせ中よ。」
設問:
マイケルは何をしていますか?
a. 彼はベイカー先生と一緒に理科を教えています。
b. 彼はベイカー先生と話をしています。
c. 彼は自分の教室へ歩いています。
d. 彼はジョーンズ先生にいくつか質問をしています。
- 「Can I help you?」は定番の会話表現。「いらっしゃい、どうしたの?」の意味で、日常会話にも頻出。
- 「in a meeting with ~」=「~と打ち合わせ中」も覚えておきたい実用表現。
- 問題文を読む前に、**登場人物の関係と話題(school / class / teacher)**を意識すると聞き取りがスムーズになります。
第1問 2番
Naomi: I’ve studied American history and culture for three years.
Tom: That’s great. Why did you decide to study it?
a. Because I wanted to understand the details of American movies.
b. Because I met American people two weeks ago.
c. Because I wanted to know European history last year.
d. Because I was touched by traditional Japanese culture.
和訳:
トム:「ナオミ、アメリカでは何を勉強したの?」
ナオミ:「アメリカの歴史と文化を3年間勉強しています。」
トム:「それはすごいね。どうしてそれを勉強しようと思ったの?」
設問:
ナオミは次に何と言うでしょうか?
a. 私はアメリカの映画の細部を理解したいと思ったからです。
b. 私は2週間前にアメリカ人の人々に会ったからです。
c. 私は去年ヨーロッパの歴史を知りたいと思ったからです。
d. 私は日本の伝統的な文化に感動したからです。
a. ティムとサリーはメアリーに自分たちの写真を見せています。
b. メアリーとサリーは数か月の間お互いを知っています。
c. メアリーはサリーの親友で、テニスが得意な選手です。
d. ティムとメアリーはこれまでサリーに会ったことがありません。
第1問 3番
Sally: This is Mary, my best friend. Tim, you’ve met her once before, right?
Tim: Oh, I met her a few months ago. She’s good at playing tennis, isn’t she?
Sally: That’s right. We’ve known each other for two years.
a. Tim and Sally are showing their picture to Mary.
b. Mary and Sally have known each other for several months.
c. Mary is Sally’s best friend and a good tennis player.
d. Tim and Mary have never met Sally before.
和訳:
ティム:「サリー、その写真を見せて。オレンジのシャツを着ている女の子は誰?」
サリー:「この子はメアリーよ。私の親友なの。ティム、前に一度会ったことあるでしょ?」
ティム:「ああ、数か月前に会ったよ。テニスが上手なんだよね?」
サリー:「そうなの。私たちは2年間の付き合いなの。」
設問:
この会話について正しいものはどれですか?
a. ティムとサリーはメアリーに自分たちの写真を見せています。
b. メアリーとサリーは数か月の間お互いを知っています。
c. メアリーはサリーの親友で、テニスが得意な選手です。
d. ティムとメアリーはこれまでサリーに会ったことがありません。
第2問
We lost the game, and we were very disappointed then. I think it is important to learn from losing, and then we decided to communicate more with each other during the practice. Next time, we will win!
問1
What did Masato and his team members start to do after the rookies’ game?
新人戦のあと、マサトとチームメイトは何を始めましたか?
a. They started to practice harder.
→ 彼らはもっと一生懸命練習を始めました。
b. They started to get tired easily.
→ 彼らは簡単に疲れるようになりました。
c. They started to become more nervous.
→ 彼らはより緊張するようになりました。
d. They started to communicate more.
→ 彼らはもっとお互いにコミュニケーションを取るようになりました。
文中の “we decided to communicate more with each other”
(私たちはもっとお互いに話し合うことに決めました)
という部分がそのまま正解の根拠になります。
「decided to = ~することに決めた」と聞き取れるかがポイントです。
問2
What is true about Masato’s speech?
マサトのスピーチについて正しいのはどれですか?
a. He started basketball last month.
→ 彼は先月バスケットボールを始めました。
b. He experienced many games a year ago.
→ 彼は1年前にたくさんの試合を経験しました。
c. His team lost the rookies’ game.
→ 彼のチームは新人戦で負けました。
d. His team won the second game.
→ 彼のチームは2回目の試合で勝ちました。
スクリプト中の “We lost the game, and we were very disappointed.”
(私たちは試合に負けて、とてもがっかりしました)
が根拠です。
リスニングでは「lost(負けた)」と「won(勝った)」の聞き分けがとても重要です。